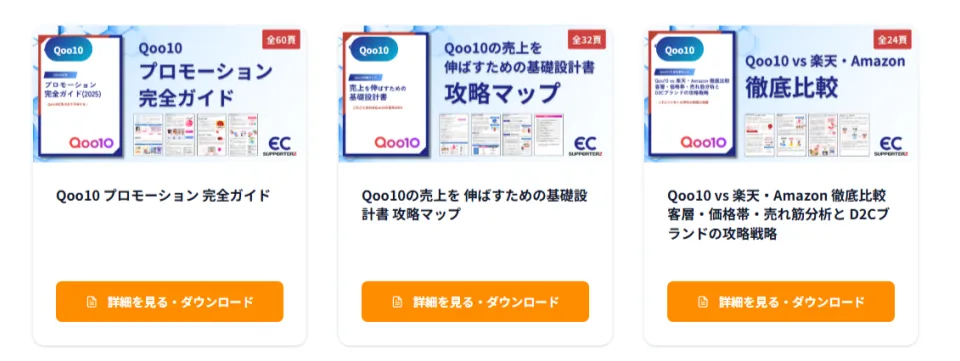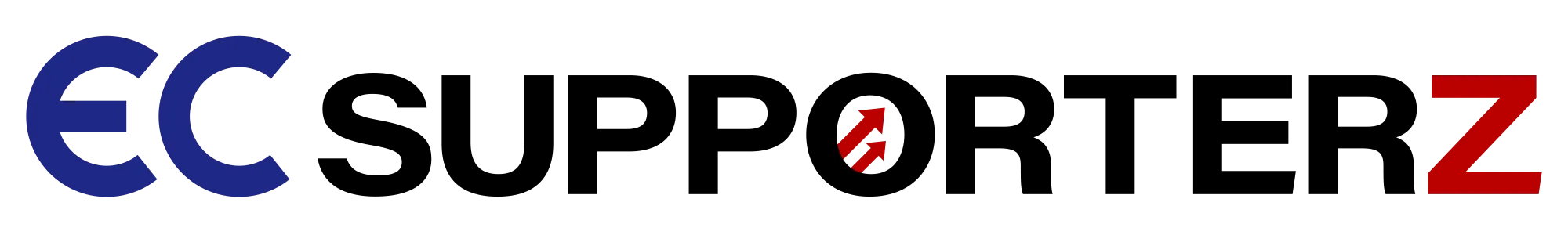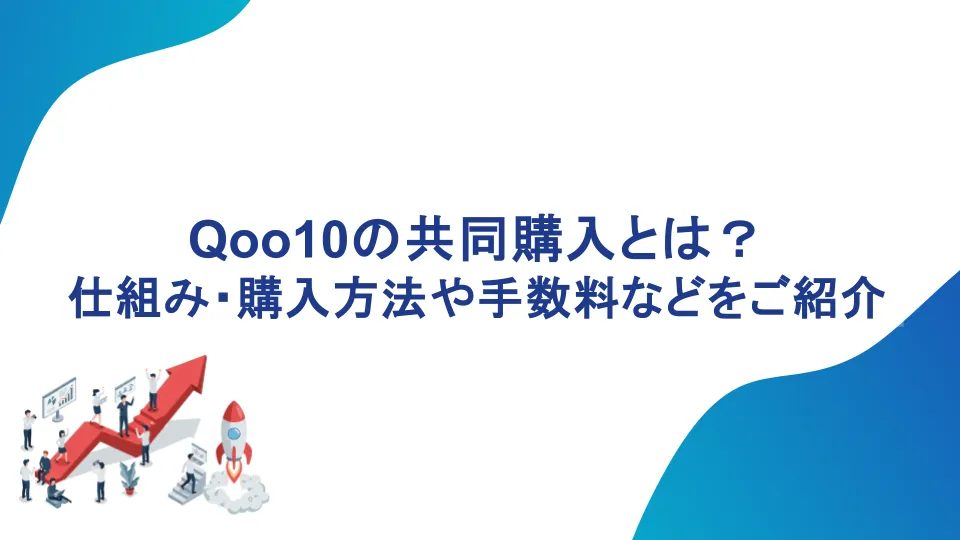ECモール「Qoo10」で、最近注目を集めている購入スタイルが「共同購入」です。
「みんなで買うことで、価格が下がる」――そんな仕組みがあるのをご存じでしょうか?
通常よりもお得に商品が手に入るこのシステムは、Qoo10を利用する若年層を中心に人気を集めています。
この記事では、Qoo10の共同購入の仕組みや購入方法、出品側のメリット・注意点、さらには設定手順までを詳しくご紹介します。
「どうすれば参加できるの?」「手数料はかかるの?」といった疑問をお持ちの方も、この記事を読めば一気に解消できます。
Qoo10での販促にて新しい切り口を探されている運営者は必見の内容です。
Qoo10の共同購入とは?

共同購入の仕組みと特徴

共同購入(グループバイ)は、一定期間内に設定した目標販売数を達成した場合のみ割引販売が成立するQoo10独自の企画広告です。
例えば「3日間で100個売れたら10%OFF」のように目標数量と割引率を決めて利用します。販売期間は3日、7日、14日から選択でき、目標未達の場合は自動的に注文がキャンセルされます。
割引率は10%以上 or 100円以上に設定が必要で、成立した場合、割引後価格の8%(20,000円以上の場合6%)の成約手数料が別途かかります。
共同購入のメリット
一度にまとまった数量の受注が入るため、売上ボリュームの拡大と在庫消化に有効です。ユーザー側も「みんなで買えばお得」という参加型の楽しさがあり、話題性を生みやすい施策と言えます。
手数料率が一律8%(高額商品6%)と通常販売より低く抑えられる点も魅力です。
割引条件を柔軟に設計できるので、「セット購入〇組達成で〇円OFF」など工夫次第で様々なプロモーションに応用できます。また共同購入ページに掲載されることで、新規顧客の目に触れる機会も増えます。
共同購入のデメリット
割引ハードルが10%以上と高めで、利益圧迫につながりやすい点は注意です。
目標数量に達しなければ通常価格販売またはキャンセルとなるため、事前の需要見極めが難しい場合は不成立リスクがあります。
掲載には3日3,000円~の費用も発生するため、小規模ショップにはハードルが高めです。
また共同購入利用中の商品は他のタイムセールや今日の特価など他広告と併用できない制約があります。
期間中ずっと在庫を確保しておく必要もあり、在庫管理・発送負荷にも留意が必要でしょう。
共同購入に向いている商品
Qoo10ではさまざまな商品が共同購入の対象となっており、最低販売数も商品やショップによって異なります。
Qoo10の「共同購入のおすすめ商品リスト」を見てみると、下記のような商品が共同購入の対象となっています。
- モバイルバッテリー
- 充電ケーブル
- ヘアアイロン
- マニキュアセット
- 食品
- パジャマ など
共同購入には向いていないような商品がありますが、それでも多くのユーザーが購入しているため、ランキングに名を連ねています。
このことから、ショップ側は「どうせ売れないだろう」とあきらめずに、各商品を共同購入にしてみることをおすすめします。
まとめると、共同購入はユーザー同士が協力しあい、スポンサーのようにお金を出資しあって商品を購入する方法といえます。
共同購入の設定手順
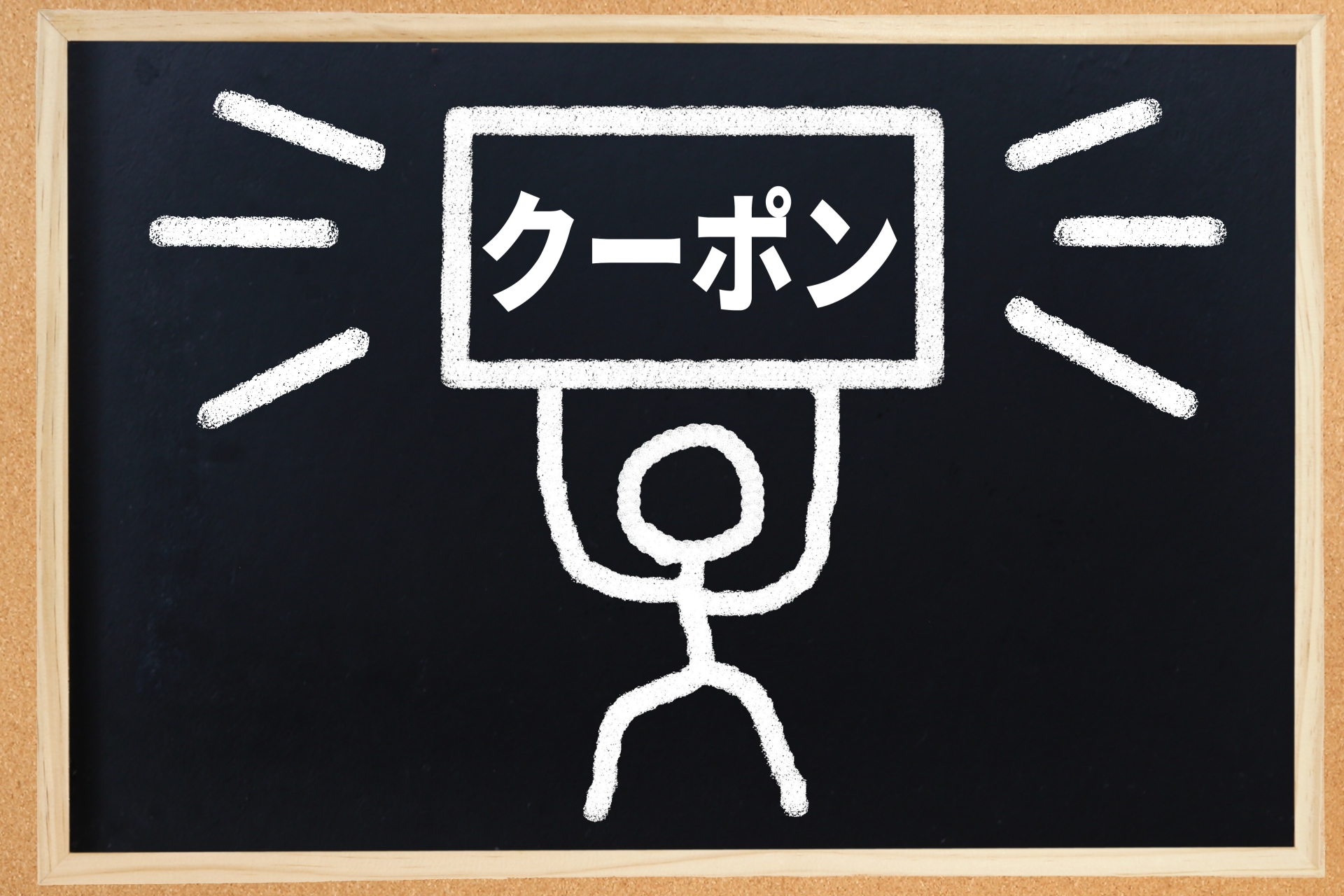
1. J・QSMにログイン
まずはJ・QSM にログインします。
その後、メニューにある「共同購入の商品情報」ページ内の、「検索」をクリックして、共同購入に設定したい商品を検索します。
検索結果から該当商品を選び、「選択」をクリックして商品を選びます。
2. 各種設定
商品を選定後、共同購入を達成するための条件を決めるため、下記を設定します。
成立価格(割引後の販売価格)
通常価格の10%以上、もしくは100円以上を割引する必要があります。
成立価格を入力すると、自動計算で供給原価(生産金額)を表示します。
手数料については成立価格(割引後の販売価格)の8%で、自動で算出されます。
通常価格(割引前の販売価格)
通常価格(割引前の販売価格)は名前の通り、割引を適用する前の価格を指します。
通常価格も共同購入に関するページに表示される要素であり、どれだけお得になっているのかをユーザーに示すことができます。
成立価格を率か額のどちらで考えるのかについては、ショップの経営方針や商品単価などによって変えましょう。
成立数量
成立数量とは、競合購入を設定している期間中の注文数を指すものであり、こちらの数値を上回らなければ販売されません。
こちらについては1個から設定が可能であり、期間中の注文数量が成立数量に達しなかった場合は、自動的にキャンセルされます。
生産予定数などを検討して、販売の実現が可能な最適な成立数量を設定しましょう。
数量制限を入力(選択事項)
Qoo10における共同購入の数量制限とは、ひとりあたりに購入できる数量を制限したい場合に入力するものです。
ユーザーのなかには、アイテムを独占して転売するために、アイテムを独占しようと考えている人がいます。
一方、数量制限を1にすると、共同購入の数量に達しない可能性が上がるため、最適な数量を設定しましょう。
期間
共同購入は開始日時と終了日時を設定することができ、その際は必要なQキャッシュを確認します。
いわゆる受注期間を設定できるというものであり、この期間内に購入したユーザーに対して、数量を満たした場合に販売できます。
設定可能な期間は開始日時は当日から1ヶ月先まで、終了日時については特に設けられていません。
自動成立設定
共同購入の自動成立は「はい」「いいえ」「保留」の3つから選ぶことができ、下記のように条件が決められています。
- はい :1件でも注文が発生した場合、商品を発送
- いいえ :成立数量が2個以上で、成立数量に達しなかった場合、自動キャンセル
- 保留 :成立数量が2個以上で、成立数量に達しなかった場合、キャンセルを行うか否かを3日以内に決定
ただし、成立数量を1にした場合、必ず「はい」を選ばなければなりません。
発送可能日
共同購入は成立日時が明確になっていないことから、具体的に○○日に発送といった約束はできません。
そのため、共同購入のアイテムは発送可能日を下記のように設定します。
- 当日発送 :当日発送が可能な商品に設定
- 一般発送 :発送処理までに1~3営業日かかる商品に設定
- 商品準備日の設定 :4日から14日の間で設定
3. ポップアップの内容を確認
一通りの情報を入力し、「+追加」をクリックしたあとは入力情報が記載されているポップアップが表示されます。
内容を確認し、問題なければ「OK」をクリックして情報を公開します。
間違いや修正箇所があれば「キャンセル」をクリックし、対象箇所を修正しましょう。
4. 情報の確認
設定した共同購入は、共同購入の商品情報から【開始前】をクリックすることで確認できます。
また、進行中の共同購入についてはその期間を変更できるため、適宜変更対応を行いましょう。
これらを確認し、共同購入で販売しているアイテムが指定数に達したとき、下記の数式で売り上げが精算されます。
精算金額 = 割引後の販売価格 – (割引後の販売価格 × 8%)
たとえば、通常販売価格が2,000円、共同購入で200円割引した場合、下記の数式で計算します。
- 通常 :2,000円 – (2,000円 × 手数料10%) = 1,800円
- 共同購入 :{2,000円 – (2,000円 × 手数料10%)}-(2,000円 ×共同購入の手数料8%) = 1,656円
一見通常価格よりも共同購入のほうが少ない利益額になりますが、これはアイテムひとつで考えた場合によります。
多くの共同購入商品はひとつ以上であり、購入数が多くなるほど残る利益が多くなるものです。
また、同じ個数を売る場合でも、通常販売の場合は期限が設けられていませんが、共同購入は期限が設けられています。
このことから、共同購入の場合は期間の収益が確定していることが差別化要因として挙げられます。
共同購入の注意点

共同購入サービスを提供する際は、下記のポイントを理解しておきましょう。
「共同購入」の対象であることを明記する
ユーザーのなかには、購入したいアイテムが共同購入に対応しているのかどうかが分からないといった人がいます。
共同購入はまとまった利益を獲得できる可能性がある販売方法のため、できる限り多くのユーザーに知ってもらいたいものです。
ユーザーに共同購入の対象であることを知ってもらうためには、タイトル部分に記載することをおすすめします。
多くの商品ページにはタイトルに共同購入という情報が記載されていないことから、気付かれないことが多いのです。
一方、【共同購入】という文言をタイトルに含めると、それが共同購入のアイテムであることを一目で理解します。
Qoo10のページを見てみると、タイトルの一番はじめに共同購入に関する文言を記載しているページが多い傾向にあります。
お得であることをアピールする
先述の通り、共同購入では通常価格の10%以上、もしくは100円以上の割引を必ず設定しなければなりません。
商品によって割引額なのか、割引率なのかを判断する必要があり、ユーザーはどちらがお得なのかを一目で確認します。
同じ割引額・率でも、表現方法によってお得に見えたり、お得じゃないと感じたりするものです。
たとえば、1,000円のものを900円で販売した場合、割引率は10%、割引額は100円になります。
どちらも同じことを伝えていますが、ユーザーによってどちらのほうがお得に感じるかは異なるものです。
一般的に、高額な商品は割引率、安価な商品は割引額で表現することで、反応が良くなる傾向にあります。
メガ割対象外である
Qoo10ではさまざまなイベントが開催されており、そのなかには「メガ割」と呼ばれるものが含まれています。
メガ割はQoo10において最大ともいえるイベントであり、多くのユーザーを集客できる可能性があります。
一方、共同購入についてはメガ割の対象外となってしまうため、期待しているような収益を得られない可能性が高いです。
そのため、ショップ側はメガ割に近い時期に出品する場合、共同購入にするべきなのかを選択しなければなりません。
まとめ|ユーザーに力を合わせてもらおう

こちらの記事では、Qoo10における共同購入について解説しました。
Qoo10の共同購入はショップが最低販売数を設定してから出品する仕組みで、最低販売数を上回ったときに販売する方法です。
ユーザー同士が協力しあってショップが指定した数量を達成することから、これまでのビジネスとは異なる形式といえます。
通常よりもお得な価格で購入できたり、一度の取引で大量に在庫量を減らせたりといったメリットがあります。
Qoo10における収益の上げ方を検討する際、共同購入の選択肢を含めておきましょう。
参考サイト:https://qsm.qoo10.jp/GMKT.INC.GSM.Web/Login.aspx
Qoo10攻略のヒントになるお役立ち資料がダウンロード可能
当社ではこれまでのQoo10運用実績から保有するノウハウをお役立ち資料としてご提供しておりますので、Qoo10をスケールさせていきたい事業者の方は是非資料を手に入れて運営にお役立てください。