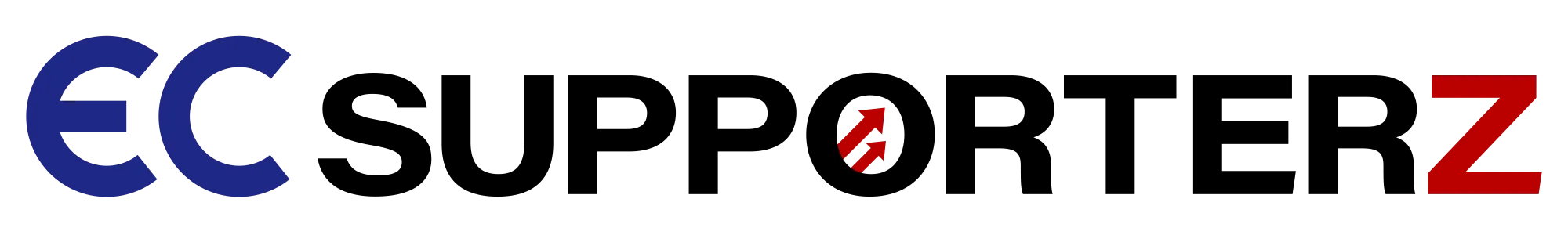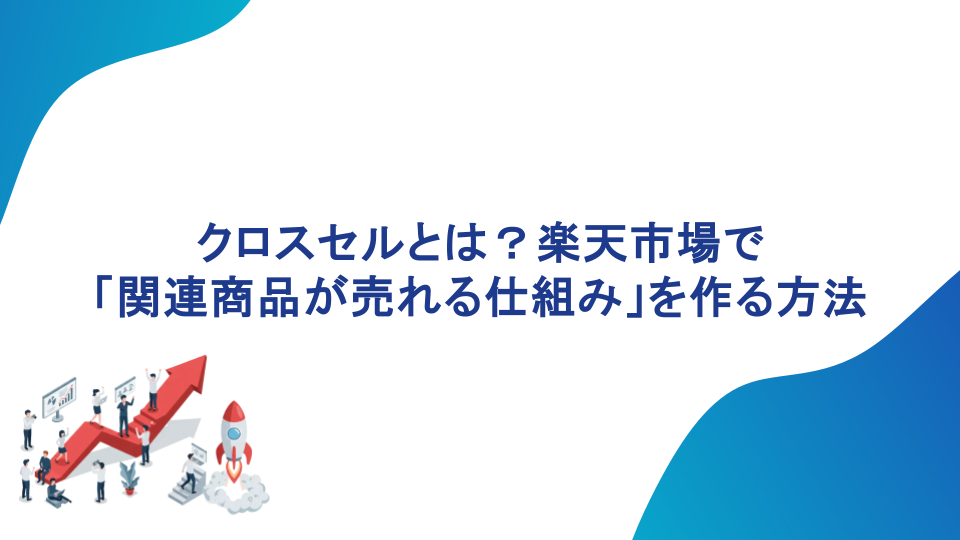クロスセルの定義とアップセルとの違い、楽天での実現方法
クロスセルとは、ある商品を購入しようとしている顧客に対し、その商品に関連する別の商品を追加で提案し、一緒に購入してもらう手法です。典型的な例として、実店舗ではマクドナルドでハンバーガー購入時に「ご一緒にポテトはいかがですか?」と勧められるケースが挙げられます。これは顧客のニーズに沿った付随商品をすすめて客単価を上げる代表的なクロスセルの例です。
一方、アップセルは現在検討中の商品よりも上位モデルや高価格帯の商品を提案し、より高価な購入に誘導する手法を指します。例えばカフェで通常サイズのドリンク注文時に「プラス料金でサイズアップできます」と勧めるのはアップセルです。クロスセルが”追加購入”なのに対し、アップセルは”代替購入”でグレードアップを図る点が異なります。

楽天市場でのクロスセル・アップセル実現方法
楽天市場のようなECモールでも、クロスセルとアップセルの概念は重要です。楽天市場では商品ページ上やカート投入時に「この商品を買った人はこんな商品も買っています」や「おすすめの商品」として関連商品や上位商品が自動表示される機能があります。これは楽天がモール全体のデータを活用して実現しているレコメンド機能で、店舗側が個別に設定しなくてもクロスセル(関連商品の提案)やアップセル(上位モデルの提案)が半自動的に行われる仕組みです。
加えて、店舗運営者自身も楽天の店舗管理システムRMS上でクロスセルを仕掛けることができます。その方法としては、後述する組み合わせ販売(セット販売)機能を使って関連商品をセット提案したり、商品ページの中で手動で関連商品へのリンクを設置して誘導する方法などがあります。
クロスセルが売上・利益に与える効果
AOV(客単価)の向上
クロスセルやアップセルを適切に活用すると、ECサイトの売上指標である客単価(Average Order Value:AOV)が向上し、結果的に売上全体を大きく伸ばすことが可能です。店舗の売上は一般的に「売上 = アクセス人数 × 転換率(CVR) × 客単価 × リピート率」という構成要素で表されます。新規客数やCVRを変えずとも客単価を上げればそのまま売上増につながるため、クロスセル施策は効率的な売上向上策となります。
例えば楽天市場の実例では、関連商品のセット販売機能(組み合わせ販売)を活用することで平均客単価が20%以上向上したケースが報告されています。また、弊社が運営代行する楽天店舗において「○○円以上のまとめ買いで使えるクーポン」を発行したところ、客単価が500円以上アップするといった成果も確認されています。

LTV(顧客生涯価値)の向上
さらにクロスセルの効果は一時的な売上増に留まらず、長期的な顧客価値の向上にも及びます。関連商品の提案を通じて顧客の満足度が高まればリピート購入が促進され、顧客一人当たりの生涯価値(LTV:Life Time Value)の増加につながります。
LTVは一般に「LTV = 平均顧客単価 × 粗利率 × 平均購入頻度 × 平均継続期間」で算出されます。クロスセルにより客単価が上がり購入頻度も増えることで、この式の複数要素が底上げされ、結果的に顧客一人当たりから得られる売上・利益が最大化します。
また既存顧客への追加提案は新規獲得に比べマーケティングコストが低く抑えられるため、費用対効果(ROI)の面でもメリットがあります。クロスセルは顧客にとって「必要かもしれない商品を教えてくれる」親切な提案でもあるため、満足度向上やブランドロイヤルティ強化にも寄与します。
楽天RMS内でできるクロスセル施策
1. セット販売(組み合わせ販売)
楽天RMSには、ある商品と別の商品をセットにして販売できる「組み合わせ商品」機能があります。RMS管理画面で「商品管理」→「組み合わせ販売設定」と進むと、セット販売の登録画面にアクセスできます。ここで親商品(メインとなる商品)と子商品(セットにする関連商品)を選び、セット価格や割引率を設定することで、お得なセット商品を作成できます。

たとえば単品では3,000円で人気の主力商品Aに、あまり売れていないがAと一緒に使うと便利な商品B(単品2,000円)を組み合わせ、セット価格を4,000円と設定するといった具合です。別々に買うより「お得に買える!」と感じさせる価格設定がポイントになります。
こうしたセット販売の提案により、「どうせ買うなら一緒に揃えよう」とユーザーの購入意欲を刺激し、一度の来店・一回の注文で複数商品を買ってもらう機会を増やすことができます。
2. 併売(関連商品の同時購入促進)
セット商品として正式に登録しなくても、関連商品の併売を促す仕掛けを作ることは可能です。手軽な方法は、よく売れている商品のページ内に関連商品へのリンクやバナーを設置することです。
たとえば商品の説明文中やページ下部に「●●も一緒にいかがですか?」といった形で別商品の紹介欄を作り、該当商品の商品ページへ誘導する導線を貼ります。これによりユーザーは閲覧中の商品と合わせて他の商品も検討しやすくなり、「関連商品も合わせて買ってみよう!」と思う確率が高まります。
3. クーポン活用によるまとめ買い促進
クーポン発行も客単価アップの有効な施策です。特に「〇円以上の購入で使える○%OFFクーポン」のようなまとめ買いクーポンは手軽に試せて効果が高い手法としておすすめされています。
例えば現在の平均客単価が2,500円程度の店舗であれば、「4,000円以上のお買い上げで10%OFF」といったクーポンを発行することで、普段は2~3千円しか買わないお客様にも「もう一品買えばお得になるなら…」と購入を追加してもらいやすくなります。実際にこのような金額条件付きクーポンを試した店舗では、客単価が500円以上アップしたという結果も出ています。

クロスセルの分析方法とツールの活用

重要な分析指標
クロスセル施策を実行した後は、その効果をきちんと分析し、データに基づいて施策を改善していくことが重要です。まず押さえておきたい分析指標や分析軸としては、以下のようなものがあります。
1. 客単価の推移
クロスセル施策導入前後で平均客単価がどう変化したかを追跡します。楽天RMSにはR-Karte(アールカルテ)と呼ばれる標準搭載の分析ツールがあり、売上やアクセス数、転換率、客単価といった基本指標を日次・月次で簡単に確認できます。
2. 併売率・クロスセル成功率
一度の注文で複数商品が購入される割合(併売率)や、クロスセルの提案が実際に追加購入につながった割合(クロスセル成功率)を分析します。ある企業の事例では、データ分析を駆使して関連商品の提示タイミングを最適化した結果、クロスセル成功率を平均35%向上させたケースも報告されています。
3. 商品間の関連性分析
購買データを活用して、自社商品の中でよく一緒に購入されている組み合わせや強い関連性を持つ商品ペアを発見します。例えばデータを分析した結果、「商品Aを購入した顧客の68%が30日以内に商品Bも購入していた」などの相関が見つかれば、商品Aの購入時に商品Bをクロスセル提案することで高確率で追加購入が期待できます。
外部ツールの活用
基本的な分析はRMSのレポート機能やExcel等でのデータ集計で可能ですが、さらに高度な分析を行いたい場合は外部ツールの活用も検討できます。最近では楽天RMSとAPI連携できる分析ツールが数多く提供されており、データの自動取り込みから高度な可視化・解析まで支援してくれます。
例えばAIを搭載した外部ツールを使えば、顧客属性や購買行動データを統合的に分析し、一人ひとりに最適な商品をレコメンドする仕組みを構築することも可能です。実際、AIによる購買データ分析を導入した企業では次回購入商品の予測精度が85%以上向上したとのデータもあります。
クロスセル設計における注意点とよくある失敗

1. 導線の設計ミス
クロスセルの提案箇所やタイミングを誤ると効果が半減します。例えば関連商品を提案する位置がページの下の方にありすぎてユーザーの目に入らなかったり、購入フローから離れた場所に誘導してしまったりすると、せっかくのクロスセル機会を逃しかねません。
対策として、ユーザーが購入を検討するタイミングに合わせて提案を差し込むことが重要です。具体的には「商品ページ閲覧時」や「商品をカートに入れた直後」などが効果的な導線となります。
2. 関連性の低い商品提案
クロスセルでよくある失敗が、「関連性の薄い商品の組み合わせ」をユーザーに提示してしまうことです。売上を伸ばしたいばかりに無理に関係ない商品までセットに含めたり、「ついでに全然別のカテゴリー商品も見せてみよう」と欲張ったりすると、ユーザーは価値を感じられず購入を見送る可能性が高まります。
クロスセル成功の秘訣は顧客の興味・ニーズに合った商品提案を行うことにあります。過去の購入履歴や閲覧履歴を分析し、ユーザーが「ちょうどそれも欲しかった」と思えるような関連度の高い商品だけをピックアップして提案しましょう。
3. 価格帯・割引設定の不適切
クロスセルで提案する商品の価格設定にも注意が必要です。クロスセルで薦める関連商品は、主商品に比べてあまりにも高額すぎない方が受け入れられやすい傾向があります。例えば1,000円の商品を見ているお客様に追加で5,000円の商品を薦めても予算オーバーと感じられる可能性が高く、むしろそれはアップセル(より高価な代替品の提案)としてアプローチすべきでしょう。
重要なのは市場価格や競合価格と照らし合わせて適正かつ魅力的なセット価格にすることです。常に「別々に買うより○円お得」「今買わないと損」と思ってもらえる絶妙なラインを探ることが重要です。
4. ターゲットの不明確さ
クロスセル施策で全ての顧客に一律同じ提案をしてもうまくいかない場合があります。顧客によって購買目的や予算、嗜好は異なるため、本来はセグメントに応じた提案が望ましいからです。
たとえば一度にまとめ買いしがちなヘビーユーザー層には高額なセットや大量購入割引を提案し、慎重なライトユーザー層にはまず関連商品1点をそっと薦めるなど、アプローチを変えると効果的でしょう。
まとめ(自然に売れる設計→分析→改善の仕組み化)
クロスセル(およびアップセル)は、楽天市場における売上拡大と顧客満足度向上の両面で非常に重要な役割を果たします。関連商品を上手に提案することで客単価の増加やLTVの向上、ひいては収益性の改善を実現できるだけでなく、顧客にとっても便利で満足度の高い購買体験を提供できます。
ただし、その効果を最大限に引き出すには場当たり的な施策ではなく、一連のプロセスを仕組み化して継続実行することが肝心です。
成功への3ステップ
- 顧客視点で「自然に売れる仕組み」を設計:おすすめ商品の選定や表示場所・タイミングの工夫により、ユーザーにとって違和感なく「一緒に買う流れ」が生まれるようにする
- データ分析による効果測定:RMSの店舗カルテや外部ツールを使って客単価や併売率などの指標をチェックし、どの施策が奏功しどこに改善余地があるかを見極める
- 継続的な改善:分析結果に基づいて提案内容や条件の見直し、表示方法の改善、ターゲット層の調整など適切な改善策を講じる
この「設計(Plan)→実行(Do)→分析(Check)→改善(Action)」のPDCAサイクルを継続的に回すことで、クロスセルの仕組み自体がどんどん最適化されていきます。一度成功パターンが確立できれば、それをテンプレート化して他商材にも横展開することで、店舗全体の売上・利益を押し上げる持続的な成長エンジンとなるでしょう。
最後に、クロスセル施策を進化させていく上では顧客志向を忘れないことが大切です。関連商品提案は単なる売上アップ手段ではなく、適切に行えば「こんな商品もあるんだ」「一緒に買えて便利」と顧客に喜ばれるサービスの一環です。その結果としてリピート購入が増え、お店のファンが増え、長期的なLTV向上につながる点を強調しておきます。
楽天市場という巨大ECモールでは競合も多いですが、クロスセル施策を上手に仕組み化している店舗は着実に客単価と満足度を伸ばし、安定した成長を遂げています。ぜひ本記事で紹介したテクニックや考え方を参考に、自店の楽天RMS運用にクロスセルの仕組みを組み込み、「関連商品が自然に売れていく」ような理想的な販売サイクルを構築してください。
🔍 クロスセル分析をもっと簡単に、精度高くしたい方へ
楽天市場でのクロスセル成功のカギは、「何が一緒に買われているか」を正しく把握すること。
RepeaTracker(リピトラ)は、楽天RMSと自動連携し、商品別の併売データやリピート傾向を一目で見える化します。

- どの商品同士が一緒に買われているかを自動分析
- セット販売やバンドル施策の根拠データがわかる
- RMSの操作が苦手な方でも簡単に使えるUI設計
📈 クロスセル・アップセル戦略の精度を高めたい方は、ぜひ一度お試しください。